2023年10月10日 5:57 PM | 投稿者名: OSARU

都電快走
カテゴリー:東江戸川電軌, 関東合運 |
コメント(0)
2023年10月4日 10:59 AM | 投稿者名: OSARU

やり直し中
カテゴリー:東江戸川電軌 |
コメント(0)
2023年9月30日 9:43 AM | 投稿者名: OSARU
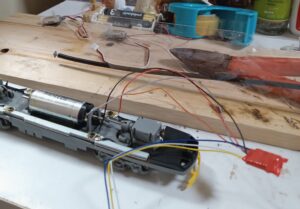
キャノンLN12が入りました
シリコンチューブに軸を挿したらゆるゆるでした
どうしようかなあ
カテゴリー:東江戸川電軌 |
コメント(2)
2023年9月30日 9:39 AM | 投稿者名: OSARU
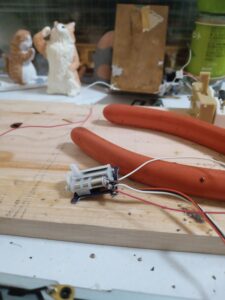
ドアエンジンの配線
カテゴリー:東江戸川電軌 |
コメント(0)
2023年9月27日 5:53 PM | 投稿者名: OSARU

前回DCCデコーダーを焼いてしまいましたので交換をしたのですが
モーターまで焼けてしまいました
トラムウェイには在庫が無いとのこと
イモンさんちでLN12を買って来ました
カテゴリー:東江戸川電軌 |
コメント(0)